「人間そのものが弱くなった」
時代と共に移りゆく武士の在り方
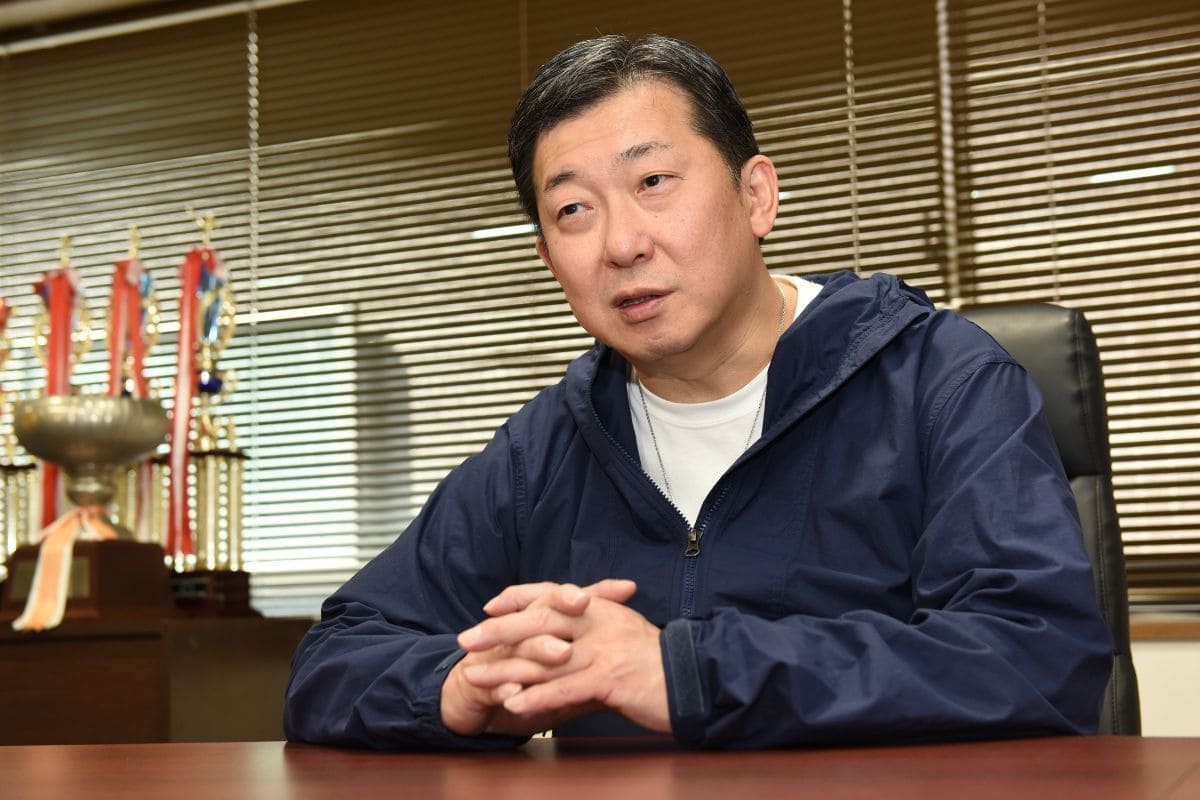
ーーー切腹を翌日に控えた古田久蔵正成(出合正幸)は、妻・良乃(竹島由夏)に「このまま死んだらどこへ行ってしまうんだろう?」「そもそも武士とはなんだろうか?」と問いかけます。武士と言えど、あくまでも人間なんだということが切実に伝わってきました。
「ひとえに武士と言っても、鎌倉時代から明治に至るまでとは全然違う存在だったと思うんです。江戸幕府が始まって戦に明け暮れていた人と、戦によって死ぬことがほぼ無くなった幕末で武士という支配階級についた者とは大きく異なる。ただ世界的に見ても、自らの支配階級に対して沢山ルールを設けたのは唯一武士だけだと思うんです。
今の専制国家を見てもそうですけど、自分たちが罰せられる法律なんか普通作らないわけですよね。でも多くの法律を作って、型に当てはめていった1つが切腹だったわけで。初期の頃は侍精神や、闘争本能から来る死生観があったんでしょうけど、幕末では平和な世が長く続いて、自らを律するという道徳や倫理は残っていたけど、人間そのものが弱くなってきた。そんな中で、自ら手を下すのは難しいですよね。だからこそ“扇子腹”というのも生まれたんだと思います」
ーーー本作で“扇子腹”の存在を初めて知ったのですが、切腹の時に刃物を用いるのではなく、扇子を腹に当てています。
「扇子で切腹する側からスイッチを入れる。自らそのスイッチを押さない限り介錯人は首を振り落とさないわけですから、自分によって死を選ぶという尊厳だけはキープされているんですね。昔は腹を刃物で十文字に切ったわけで、よくそこまでできるなと思います。それが変わった背景には、先ほど述べたことがあるんだと思います」
ーーー登場人物たちは不条理な中で生きており、生きる素晴らしさを描くのではなく、辛さや覚悟という生きる険しさがテーマとなっているように感じました。
「まさに不条理な中で死に追いやられるわけですけど、今でも自殺者が絶えなかったり、事件や事故など不条理な死はいっぱいあるわけで、それはいつの時代も変わらないと思うんです。そして不条理な死を迎えた人の親族のその後の過ごし方には個人差があって、苦しみを永遠と抱える人もいれば、意外と2、3年で傷が癒えて普通に暮らせる人もいたりして。結局は自分でどう消化するかが大事だなと思うんです。
また短編にはいなかった、しげ(笹田優花)という奉公人や、留蔵(羽場裕一)という下男が、不条理を描く上で欠かせなかったですね。同じ人間なのに、生まれた時の境遇が違うが故に身分に差がある。それを今回長編で描くことができました」
ーーー『陽が落ちる』というタイトルについて教えてください。
「やはり家族にとって父親は太陽のような存在ですし、その父親が落ちていくことを夕暮れや、夏の終わり、1人取り残された良乃など、全ての終わりというところに重ね合わせました」









