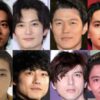「ビデオ体験で知った香港映画をさらに覆す存在」ウォン・カーワァイ

――学生時代からすでにアジア映画について書いていましたか?
暉峻「自分でも驚くところですが、ごく一般的にブルース・リーやジャッキー・チェンを知るばかりで、その当時はアジア映画にほとんど関心がありませんでした。むしろ欧米作品に興味が向いていた。だからこそ逆にその後、アジア各地でニューウェーブという動きが起きたことに心底驚けたのだと思います。
当時の日本ではアジア映画があまり新聞や雑誌で紹介されていなかったこともあります。映画館でロードショーされることもなぜか少ない。ニューウェーブというすごいことが起きているのに全然知られていない。ならば自分が紹介しなければという義務感ともニュアンスが違いますが、とにかく圧倒的につんのめっていた感覚があり、評論としてはアジア映画についてばかり書くようになりました。
今でも覚えているのは、知り合いから『アジア映画ばかり書いてると食っていけなくなるぞ』とアドバイスをもらったことです。実際はそういうことにはならず、アジア映画に急旋回して良かったなと思います」
――暉峻さんを熱狂させるようになったアジア映画はどのあたりの作品ですか?
暉峻「アジア映画に自覚的になったのは、1980年代半ばくらいだと思います。『冬冬の夏休み』(1984)や『童年往事 時の流れ』(1985)などホウ・シャオシェンの代表作、あるいは1986年のエドワード・ヤン監督作『恐怖分子』。彼らが牽引した台湾ニューウェーブはだいたい1982年くらいからです。潮流が起きたのと同時代的に出会えました。
すでに香港ではニューウェーブが起きていました。それは1978年頃からと言われていますが、こちらに関してはその頃の幸運な状況として日本のビデオ・テープ市場がバブル時代を迎えていました。メーカーがこぞって劇場公開されない映画でも権利を買い、大量に発売・レンタルしていました。香港ニューウェーブ作品もそこに含まれていました。
香港映画との出会いはビデオ・ブーム時代と重なっていたわけです。そのおかげで大量の作品に触れられました。ある時、近所の独立系ビデオ屋のカウンターにヌンチャクが置いてあるのが見えて、『ここは何かあるな』と思って入ってみると、アジア映画にこだわりを持っている店でした。そこに行けばどんなアジア映画でも借りられたことがラッキーでした」
――1997年に出版した『香港電影世界』は、香港が中国に返還された1997年7月1日に出版されるという香港映画の節目に書かれています。
暉峻「そうです。返還というタイムリミットがあったからこそ出せた本です」
――同著あとがきに「近年の筆者の香港映画に対する関心が何よりもウォン・カーワァイ及びその作品を巡って注がれてきたことの隠しようもない証拠」とあり、ウォン・カーワァイ監督への特別な思い入れと同時代の映画作家に熱い眼差しを注いでいたことを感じる一文です。
暉峻「ビデオ体験で知った香港映画をさらに覆す存在としてウォン・カーワァイが出てきました。二重に連続した衝撃みたいなものがあり、香港映画に対する自分のイメージにどんどん変革が起きていた時代です」